こんにちはnikoshiba(ニコシバ)です。
ブランディングがなぜ必要か?現在はインフレーションが進んでコストが上がり、どのように価格転嫁するのか難しい課題を小売各社が迫られていますが、このブランドがあるなしで価格添加ができるか?否かになるくらい大きな要素です。

前項専門店コンセプトの構築とMD戦略でのマーケティングとターゲットの決め方でコンセプトの重要性を学びましたが、マーケッティングポジション、ターゲットを捉え、これらを成功裏に導くためには、店舗、商品(メーカーさんも同様)などのブランドがあるか否かで、今後の展開が大きく変わります。なので、開店前から努力し、ブランドを高めるブランディングに力を注ぐべきです。
専門店におけるブランディングの必要性と戦略の考え方
ブランディングは、お客さまの視点から発想しブランドに対する共感や信頼など、お客様にとっての、価値感を高めていく戦略のひとつです。ブランドとして認知されていないものをブランドへと育て上げる必要性があります。
ここでいうブランド構築するためのブランド戦略とは、ブランドの認知を広げ、ブランドの価値を高めるために、自社のビジネス計画に沿ってブランディングを行う戦略のことを言います。
ブランドはどんなものなのか、どのような意義があるのか、どのように達成しようとするのかなどを考え、組織及びスタッフが全てが共有できるようにすることが重要です。
その手法は、高級店、高級品に限らずその対象も多岐にわたり、商品やサービス、お店、それらを供給する企業、また人や動物等様々です。
動物で有名になったのが、先日コロナ感染で亡くなった志村けんさんの、天才!志村どうぶつ園などに出演していた「わさお」などが有名ですよね。
「わさお」は今年の6月に志村けんさんを追うように亡くなった今も地域の活性化の為にブランドを生かして活躍しています。
ブランドの必要性と意義
商品、製品やサービス、ロゴ、ロゴマーク、店名などに加え、広告、製品の対象者、その企業の理念、コンセプト、消費者と製品との関わり、ショップの雰囲気やショップの店員など、さまざまな要素が混じり合って作られています。
このような、ブランドのイメージは、それぞれの消費者目線や、心にあるもので、広告やマスコミなどで宣伝し、お店や、企業が創り出し、コントロールするものもあれば、消費者によって、口コミやSNSなどで作られるものもあります。
これらを構築するツールの一つがソーシャルネットワークサービス(SNS)です。今まではTVやラジオなどマスコミでの宣伝が多かったのですが、今では無料でも使えるfacebook、instagram、ブログ、ツイッター、ライン、youtubeなどでのブランディングが必要になります。最近ではこれらを利用した広告代理業のユーチューバ―、ブロガーなどが大活躍していますよね。

それらSNSが、ブランディング戦略の中で重要ポイントとなってきています。それらを認識する必要があり、個人名をブランドにするのか、企業名をブランドにするのか、また、商品名、店舗名など戦略を決める必要があるのです。目標を決め、計画的にブランディングする為には何をブランディングして踏み出すのかを決めることです。
ブランディングの考え方
有名な例では、タオル業界が倒産の危機に瀕してたものを、タオル業界が力を合わせて、ロゴマークを統一し「今治タオル」と言うブランドを構築し、ブランディングで、こだわりの商品開発をし、一躍日本のトップブランドにしたのが有名な話です。
皆さんもこのブランディングが開店前から始まり開店後も最重要課題として認識をすることだと思います。ブランディングについてはまた別の販促の項で出てくると思います・・・
これらを生かして自店、自社のイメージを確立するために、内外装、商品などを同時に戦略を決めた上で構築していきます。
現在コロナ禍で実在の店舗は家賃負担、人件費負担で窮地に追い込まれています。しかし、通販をやるにしてもリアル店でもブランドの必要性は明らかです。
なぜならば商売は信用第一だから、信用=ブランドがあるなしでは大きく信用が違います。
今後、コロナ禍の落ち着いた後には必ず大きなチャンスが来ると考えて勉強していくことが必要だと思われます。
ブランディング戦略
店舗の立地は、どのような業種で、どのような店舗イメージ(ブランド)を目指すかがで異なります。例えば、コダワリの雑貨発想の業種なら住宅街を背景とする地域で、広範囲な商圏が望ましいと思います。なぜならば、生活圏の、全体顧客シェアーで5%の確保を目指し、リピーターをいかに確保するかが戦略として考えることができます。
インターネットによる情報化時代では、商圏を広く取り、注目してもらえる、よりこだわった戦略が必要なのかも知れません。
店舗の内外装はコンセプトに合った商品を、引き立てる内装にし、いかに販売増に繋げるか。お客様を商品だけでなく、内外装の雰囲気によって来店誘因を図れるか、であり、また、そこで接待するスタッフも、イメージの一部と考えて、一体化を図ることが重要であり、ポイントになります。
この一体化を踏まえての仕入れ手法、販売手法があれば、私は量販店の売り場も活性化が可能だと考えています。
多くの量販店は価格を安くし、良品廉価の従来型のスーパーに戻しつつある(今回のインフレで戦略が変わりつつあります)が、これはこれで有効な手段であると言えるのですが、ユニクロ、ニトリ、イケア、無印良品との差が開いていくのはこの辺にあるのかもしれません。
小さな専門店、カフェや、競合が多くなった美容室、その他の業種も、これらのことを踏まえ、自店独自の小回りの利く戦略「ウチにしかない」を考えると良いでしょう。こんな古民家風のカフェも、立地がへんぴなところを逆利用して繁盛しているところもありますよね。美容室なども和のコンセプトを取り入れるのも面白いですよね。
ブランディング例
イタリアンのお店でも私の知り合いのお嬢さん夫婦が経営している
Grigio a ao https://www.facebook.com/Grigio-e-ao-236137996865321
さんなども、その一例だと思います。能勢の小さな村ですが大阪、京都、奈良、神戸からも1~2時間もかけてお客様が訪れます。
自然が大好きなご夫婦は小さな一軒家を買って、自分たちで改装を加え3年ほど前に開業なさいました。今では人気のお店になって予約制になっています。

よろしければ、一度訪れてみてください。きっとあなたの隠れ家的なお店になりますよ。TEL072-703-1298でご予約下さい。このような癒し空間での食事、素敵ですよね。

もちろん、物販店でもこのような発想を取り入れ、商品ばかりの販促が目立つ中で、本来は内外装イメージ、カテゴリー分類での関連性を持たせたイメージ、棚台ごとのイメージ、商品のイメージ、商品の並べ方のイメージ、そして、顧客接待のスタッフイメージ(スタッフは女優、男優である)を独自に、トータルで考えると良い結果が出ると思います。
【じゃらん】国内25,000軒の宿をネットで予約OK!2%ポイント還元!![]()
今回のコロナ禍で、医療従事者と関連の方々のご苦労に頭が下がります。感謝をしたいです。皆様も感染対策をなさって大変な生活だと思います。これ以上、感染が拡大しないことを祈っています。
そして、経済は大変な状況ですが、中小企業、個人企業の方々のヒントになり、業績が回復され、スマイルライフになれますようにお祈り致します。
事業のご案内 nikoshiba(ニコシバ)
現在は、専門店チェーンを45年間にわたり経営をしていた実績を生かして、小売業コンサルとして、開業支援や、小売店のノウハウ、システム運営他、M&A、事業承継などのご相談を賜っています。
当時開発した販売POS&受発注のシステム(ぺーパーレスでの受発注システム)、ABSCアプリなどもご案内できますし、経験からホームページの作成なども専門店ならではのアドバイスや、SEさんなどのご紹介もいたします。
その他、高齢者、初心者の方のスマホやPCのこと、健康や日常生活で少しでもお役に立てるといいなとの思いも含めアップしています。ご笑覧賜れば幸いです。

開業支援、専門店効率化
◉専門店の運営のお手伝い
初めての小売店、専門店運営をお考えの方に親切にアドバイスをいたします。
詳しくは 専門店マニュアル
◉専門店を開業したい方、ショッピングセンターへお店を出したい方
店舗開発から、店舗内装のご相談、仕入れ先開発など、開業支援のコンサル・POS販売管理・ペーパーレスでの受発注システムなどのご案内を致します。
詳しくは ショップ販売戦略
◉テレワークでのシステム化、ペーパーレスで大幅な削減をしたい方
詳しくは 販売POS&受発注アプリ ABCSアプリ(アプリケーション・ビジネス・コントロール・システム)
ホームページ作成・AI、顧客管理アプリなどの制作もご相談ください。
事業承継、M&A
◉経営上のお悩み相談、事業承継、M&Aなどのご相談も賜ります。
経営者の皆様の立場での悩み相談、事業承継などお気軽にご相談ください。
経営難の会社さんの社長に寄り添っての、お悩み相談、アドバイス等、失敗の経験からのお手伝いをしています。事業承継や、M&Aのご紹介も㊙️で可能です。お気軽にご相談くださいませ。
どうしても、ご継続を断念なさる場合も、ひょっとして継続を模索できるのではの可能性も含めて、経験からのご相談、アドバイスを賜ります。
nikoshibaブログ に戻る
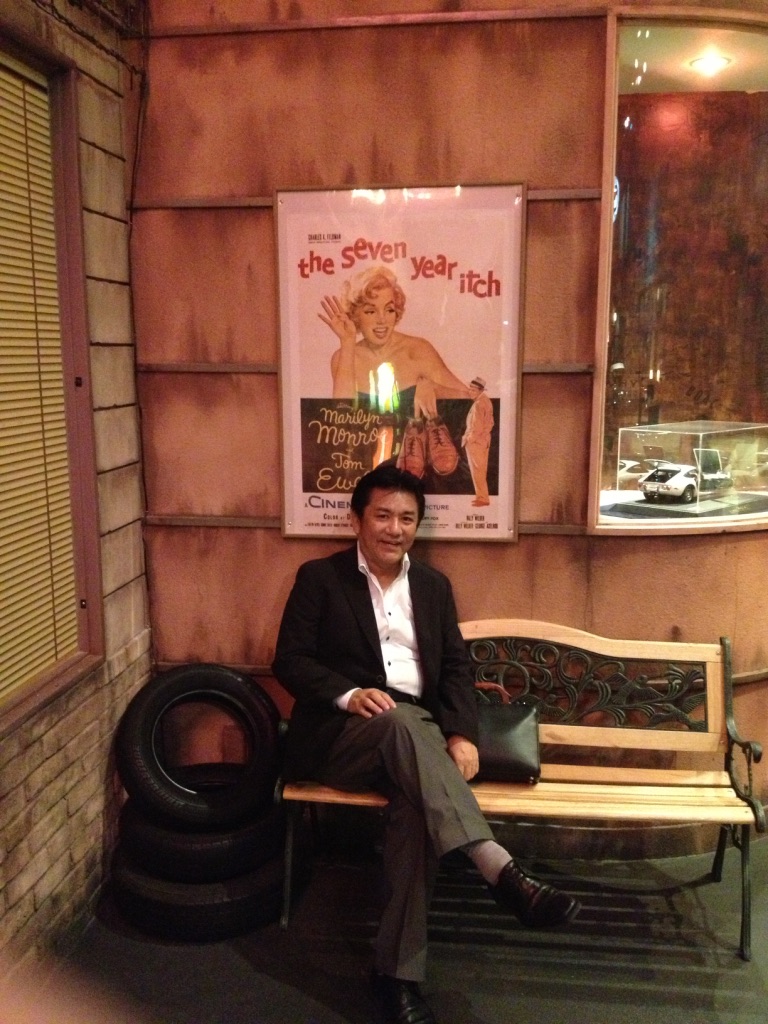
お気軽にお問い合わせください。
2〜3日中にご連絡をさせていただきます。
お問い合わせは無料です。
◉ABCSアプリ、小売店、その他のご質問などは、このHPの「お問い合わせ」からお願いします。









